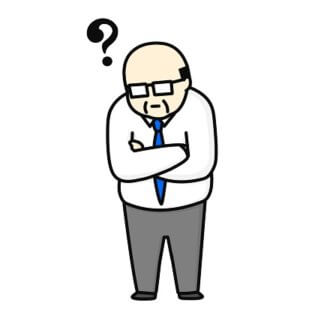
たまに「売れると興味出なくなる人はその人達が好きなんじゃなくて、マイナーアーティストが好きな自分が好き」みたいな言説を見たりするのですが、どちらかというとアーティスト側が売れる施策(キャッチーな曲や極端な商法)を取った結果、刺さらなくなった場合の方が多いのではないかと感じる
— 何やっ天皇陛下 (@emmo_takenawada) February 6, 2025
【関連記事】


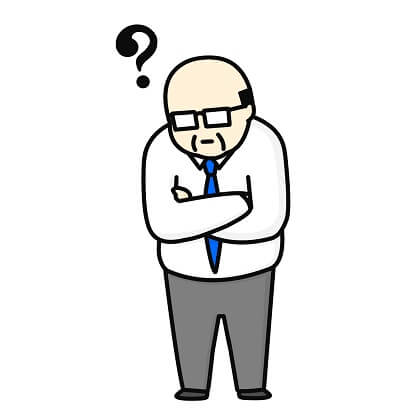
アルバムごとに雰囲気違うのは長いアーティストには良くあることでファンを飽きさせる奴が悪いだけ
なんか応援する意味なくね?みたいになる
嫌いになると言うよりは応援する気がなくなる
ふわっふわしてて草
友達でヴィクターに所属してるヤツおるけど、技巧系の曲じゃなくてメロディがわかりやすい曲にしてくださいって言われてる
あとライブ中のMCとかも台本作って送って添削されてる
そういうの漏らす時点でダサいよね
ダサさとか気にしてて草
アーティスト側が売れる施策を取って変わるのかどうかの話の1例として、メジャーレーベルに入ったら曲の方針とかも決められるから可能性としてはあるよねって話や
いやそのくらい当たり前の話というか前提の話やと思うんやが。ショービジネスなんやから
作曲家っていう職業が存在するくらいやからね、やりたい曲じゃなくても仕事で作りますって割り切ってる人も結果的に客喜ばせてたらそれでいいと思うわ
一度売れると色んな人との関わりが増えてそうもいかないんだろうな
スピッツが一曲大ヒット出した時にこれで好きな音楽やれる、売れなくなってもこの曲で営業すればやっていけるって思ったってインタビューで言ってたけどそのくらいの気持ちで狙わない奴が何ほざいてもなぁって感じ
なんかテンション高い奴が集まると冷める
仕事やぞ
引用元: https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1738888363/
音楽は人気が出ると冷める? その心理と背景を解説
「好きだったアーティストが売れると興味がなくなる」という現象を経験したことがある人は多いのではないでしょうか? これは一部の音楽ファンにとっては共感できる感覚であり、SNSなどでも定期的に議論されるテーマです。 では、なぜこのような心理が生まれるのでしょうか?
1. 「自分だけが知っている」優越感が失われる
人は、自分だけが特別な何かを知っていると感じることで、優越感を抱くことがあります。 特にマイナーなアーティストやインディーズバンドを応援していたファンにとって、 そのアーティストがメジャーになり、世間的に広く認知されることで「特別感」が薄れてしまうのです。
こうした心理は「スノッブ効果」とも呼ばれ、一般的に流行すると価値が低く感じられるという現象として知られています。
2. 音楽性の変化によるギャップ
アーティストが売れる過程では、より多くの人に受け入れられるために音楽性を変えることがあります。 例えば、
- キャッチーなメロディを取り入れる
- よりポップなサウンドへ移行する
- 大衆向けの歌詞やテーマを選ぶ
こうした変化が、初期のファンにとっては「売れ線に寄った」と感じられ、距離を置く要因になり得ます。 実際にメジャーレーベルに所属すると「技巧的な曲ではなく、分かりやすいメロディにしてください」といった指示を受けることもあるそうです。
3. 応援する必要がなくなる心理
「もう自分が応援しなくてもいい」と感じるファンもいます。 インディーズ時代には「このアーティストを支えたい」という気持ちがあったものの、 メジャーデビューして成功すれば、応援しなくても十分やっていけると思ってしまうのです。
これは「希少性の原則」に関係しています。 何かが珍しいからこそ価値を感じるという心理があり、アーティストが大衆的になると、 その希少価値が薄れてしまうため、興味を失う人もいるのです。
4. コアファンとライト層の対立
売れることで新たなファン層が増え、元々のコアなファンと新規のファンの間に軋轢が生じることもあります。 SNSでは、「昔からのファン」と「新しく知ったファン」がぶつかることも珍しくありません。 このような状況を嫌って、距離を置く人もいます。
また、流行することで過度なメディア露出が増え、「推し活」としての熱量が冷めることもあります。
5. アーティスト自身の変化
売れることでアーティスト自身も変化します。
- ビジネスとしての側面が強くなり、商業的な戦略を意識せざるを得なくなる
- インタビューやメディア露出が増え、パーソナリティが明確になることで幻想が崩れる
- 本人のやりたい音楽と求められる音楽のギャップが生じる
この変化により、初期の頃の「純粋に音楽を楽しんでいた姿」との違いを感じ、冷める人もいるのです。
まとめ:音楽をどう楽しむか
「売れると冷める」という感覚は、音楽ファンの心理として自然なものですが、 その一方で、アーティストが進化し続けることも重要です。
- 変化を受け入れて一緒に成長するか
- 自分の好みに合うアーティストを新たに探すか
音楽を楽しむ方法は人それぞれ。 変化に寛容になれば、新しい発見があるかもしれませんし、 昔の楽曲を大切にしながら、次の「推し」を探すのも一つの楽しみ方です。
9999: V系まとめ速報がお送りします 2099/0/00 99:99:99
■【画像】Z世代人気環境で最強クラスのボカロP、とんでもない屈辱を味わってしまう…
■【悲報】美少女声優さん、結婚相手に『年収800万円』を要求して炎上
■【動画】粗品にプロポーズされたあのちゃん、本番中に泣き出してしまうwwwww
■こっちのけんとが活動セーブへ 持病と向き合う「鬱期を楽しんでまいります」








コメント
椎名林檎はキャッチーな曲から徐々にスルメ曲に移行していった
人気が出ると冷めるやつは、選民意識が強いんだろうな。
人気出てから調子に乗ってドラマの準主役になったりすると熱が冷める
スピッツはロビンソンは狙っていたわけでは無いような
空の飛び方がオリコン10番代になって本人達は満足していたらしいし
狙ってたのは裸のままでの方だな
ミリオンいけると思っていたんだっけ?w
ならせめてもう少しまともなMV作れよって感じだったけど
別に売れ線狙い始めてもアルバムは自分達の好きな音楽も入れてるアーティストが多いだろうし、
やっぱただマイナーアーティストが好きなだけなんじゃ?
古い曲だと新規のバージョン違いを名乗って入れてくる場合もある
方針が変わったから嫌いになったならそっちを理由にするだろ
B’zはCD売り上げ日本一になった95年を境にやりたかったハードロック路線になってやりたい事やり続けてるな Real Thing Shakesとかようリリースしたわ
売れる方に舵きって実際売れたアーティストってそんないるんかな?
露骨に方針変えて成功したのってミセスくらいでは?
昔だったらエレカシ
>露骨に方針変えて成功したのってミセスくらいでは?
昔だったらBUCK-TICK
ビートロック路線の80年代と本格的オルタナロックに深化した90年代以降ではまさに別バンド
真っ先にKing Gnuが浮かんだし当てはまりもする気がした
ブリグリもそう
ドラマタイアップついた3枚目のシングルからかなりJPOPに寄せて実際大ヒットした
ミセスは過去から現在まで全部の曲好き
ドラマやCMやアニメのタイアップ曲でブレイクしてしまってその曲の前からいるファンとその曲でファンになったニワカのどっちを取るかで悩むってのは昔からあるな
レコード会社は当然ブレイクした曲の路線を続けて儲けたいだろうしさ
自分で好きで聴く分には人気なんて気にしたこと無いな
売れてても売れてなくても聴くし
聴く機会が多いほど馴染んでくるという人間の性質も十分わかってる
ドームとかのでかい箱でやるのが事実上のゴールだからなあ
それ以降は右肩下がりで毎年変わり映えのないライブしてばかりになる
とはいえそれで何十年も生き残ってんのは皆バケモン
確かに
B’zはデビュー36年にしてようやく紅白初出場果たしてようやく日の目を浴びてめちゃくちゃ嬉しかったけどなぁ
売れて嬉しくないって感覚分からんわ
わかる。自分の好きなアーティストが売れれば売れるほど嬉しい
Z世代というマグネシウム燃焼世代がそれを言ったら笑うしかないわ
火をつけて燃やすとめっちゃくちゃ光るのにすぐに冷めて灰になる
売れる様になるとミーハーが増えて昔からのファンはやりにくくなるっていう気持ちよくわかるよ。
俺も野球のライオンズファンだった頃森監督と清原が入って毎年優勝が当たり前になった頃からマナー守らないミーハーが激増してやりにくくなり最後はチームからバイバイしちまったからな
匿名改め鷹今みこより
V系がブームの頃
メジャーデビューするも曲が万人ウケになったり
衣装やメイクが薄くなりそのバンドの世界観が無くなり
古参ファンが去り、新規ファンも掴めず解散ってケースが多かった。
そんな中何十年もコンスタントに活躍してるのが本物だと思う。
売れたら冷めるのではなく
アーティスト側は売れることを第一にしてる。
ファンは売れる前からの世界観や大衆受けしない曲を求めてると
両者の間に齟齬が生まれるから離れていくんだと思う。
TOMOOデビューから好きだけど、今も好きだぞ
これはマイナーなアーティスト好きな自分が好きなのはあって、売れたら好きじゃなくなることへの批判を避けるための言い訳が主だな 自分自身に対しても
そのくらいで好きじゃなくなるなら、元々「好きってことにしてた」だけで大して好きじゃなかったんだよ
そのアーティストや曲の良さが周囲にも広がって(知って)ほしいと思ってるタイプのファンだったら
「ああ、売れて自分の目的は果たせたな…」と熱心な活動からは引いていくパターンもあるだろうね。
自分主体じゃなくて親目線的な意識が強めな活動ファンで。
クラリスはカレンが加入して興味が半減し顔出ししてもういいやってなってカレンが辞めて2人新しく加入を知りもうどうでもよくなった
ファンだったミュージシャン
新譜暇つぶし
売れてからはもうどうでもいい
具体例を上げるとあるにはあるんじゃん?主にKing Gnuの話に聞こえるがw星野源もタイアップ曲だけは良くないとたまに非難されたりするし、あいみょんも愛を伝えたいだけだとかだけは好きでそれ以降は聞いてない
斜に構えてるわけでも思い入れがあるわけでもなく、アーティスト本人がやりたい曲を作ってる時と売れ線やタイアップが=じゃない場合、そういう曲だけは単に興味がなく、またやりたい曲作り出せば戻るみたいな事は割と良くあるかも
RADWIMPSもそうだな
個人的には新海誠に出会ってからの曲も好きなので問題ないが、揶揄やおしゃかさまが好きなんだあれが聞きたいと言う古参ファンもいるにはいるし、ああいう人達はマイナーだからファッションにしてるわけじゃなく本当に揶揄が好き
そういうのはあると思うで